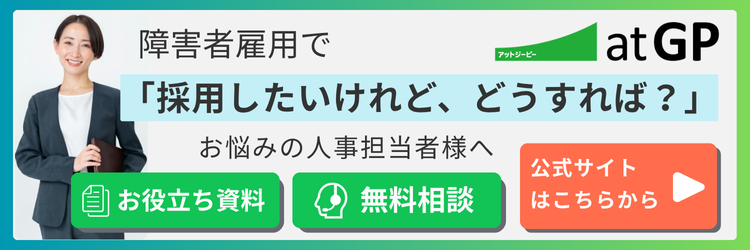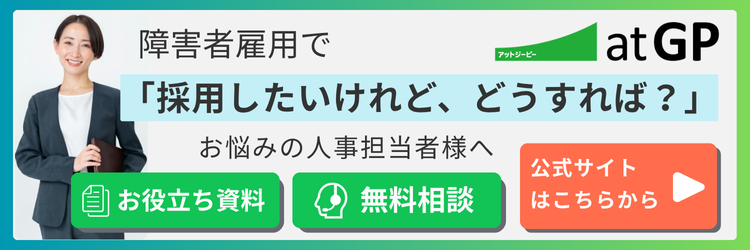「仕事を任せられない」と諦める前に「背景」を確認しましょう
入社後サポートをさせて頂いていると、障害のある社員が、業務を上手く進められなかった場合に、すぐに「この仕事は出来ないのかな」「この仕事は難しすぎたかな」と考え、業務を任せるのを辞めてしまったり、場合によっては「この人は仕事ができない」とマネジメントを諦めてしまうというケースに出会うことがあります。
企業側の戸惑いや困り感も分かります。ただ、このような状況は、非常に「もったいない」と感じます。というのも、このようなケースの中には、本来はしっかりと業務を遂行できる能力やスキル、そして意欲があっても、障害特性やこれまでのトラウマといったつまずきにより、本来のパフォーマンスを発揮しきれていないというケースが多く含まれているためです。
このような場合、コミュニケーションを重ね、課題の原因を排除、もしくは低減することで、本来のパフォーマンスを発揮できるケースが多々あります。
そのため、「仕事を任せられない」と諦める前に、ぜひ課題の「背景」は何か「原因」は何なのかを、障害のある社員と一緒に掘り下げて頂きたいと思います。
背景と対策を共有するために面談を行いましょう
障害のある社員の業務遂行の課題や、その背景を共有し対策を検討するためには、しっかりとコミュニケーションをとることが必要です。面談はその有効な手段の一つです。ぜひ面談を実施し、状況の改善に取り組んでいきましょう。
面談の目的
企業と障害のある社員が、業務の遂行に対する課題とその背景を共有し、共通の理想や目標とその実現に向けた対応を決められることを目的として頂ければと思います。
面談の心構え
・丁寧な対話や対応を心がけ、傾聴し、理解しようとする態度で臨みましょう。
・障害のある社員の中には、過去のネガティブな経験から、不安が強い方もいますので、安心して話せる雰囲気づくりを心がけましょう。
👉課題や困りごとがあれば、企業と障害のある社員が共に考え、歩み寄りながら解決に取り組むことを共有しましょう。
👉ポジティブなフィードバックも大切にしましょう。
👉面談で得た情報の共有範囲を確認し、必要に応じて秘密が守られる場としましょう。
これらは概ね健常者社員の面談とも共有のポイントかと思います。
障害があることを特別視しすぎず、普段通りの丁寧な対応を心がけましょう。
面談の構造
・面談者…障害のある社員と上司等のマネジメント担当者で行うのが一般的です
👉障害のある社員が安心して話せる方が担当しましょう
・手段…対面やビデオ通話などでの実施が一般的です
・時間…30分から1時間程度が一般的です
面談の内容
1、まずは障害のある社員の業務の遂行に関する印象を確認しましょう
・できている点
・課題に感じている点
・困っている点
・相談相手の有無
・本人としては今後どうしたいか
・希望する配慮や支援はあるか
👉伝えることが苦手な方も多いですので、ゆっくり丁寧にきいていきましょう
2、マネジメント担当者の感じている所感を伝えましょう
・出来ている点
・課題に感じている点
・障害のある社員に対して今どのような期待を持っているか(業務面/体調面/コミュニケーション面等)
・障害のある社員に対して今後どのような期待を持っているか(1ヶ月後、3ヶ月後、6ヶ月後に対する期待等)
👉ポジティブなFBもしっかりと伝えましょう
3、業務の遂行についての困り感や課題についてはその対応を一緒に検討しましょう
・対応を検討する際はまず、困り感や課題の背景や原因について確認しましょう
例)作業に時間がかかるのはなぜ?
ー口頭での指示だけだと作業内容が理解しきれないから?
ー作業中に声をかけられると集中力が切れてしまうから?
ー求められているクオリティよりも高いクオリティで仕事しなければと思い時間がかかっている?
ー分からないことがあったときの相談先が分からなかったり、相談相手が多忙だったり、相談先との関係がギクシャクしており、相談ができず手が止まってしまうから? 等
👉本人が同様の状況に対して、これまでどう対応してきたのか、本人としてはどう工夫できそうかをヒアリングしながら検討していくと、より主体的で本人にあった対策が見つかる場合が多いです
👉障害のある社員の気持ちや考えに寄り添いながら、本人の希望する配慮や支援と企業が提供できる支援を組み合わせながら対応を決めていきましょう
👉必要に応じて、主治医、産業医、支援機関担当者からもアドバイスをもらいながら対応を検討しましょう
4、業務の遂行について共有の目標を設定しましょう
面談内容の記録
・面談で話し合った内容は記録を残し、次回の面談や振り返り等に活用しましょう
・発達の特性上、視覚化された情報の方が理解しやすい方もいらっしゃますので、この点からも資料にまとめたり、記録を都度共有することが有効です
ミスが目立つという課題があったAさんの改善事例を紹介します
以下に、ミスが目立つという課題があったAさんが本来のパフォーマンスを発揮できるようになった事例を紹介します。
【Aさん】
20代 発達障害をお持ちの方
【入社後の様子】
Aさんは、仕事に対して熱意があり、任された業務に一生懸命取り組んでいました。
しかし、入社後のOJTが終わった頃から、依頼された業務を忘れてしまっていたり、指摘されても同じミスを繰り返してしまうようになりました。状況が改善されず、注意されることもことも多くなり、次第にAさんから元気がなくなり、体調も崩しがちになってしまいました。
【ミスが増えたことへの上司の所感】
Aさんは、すごく前向きで素直な人で、活躍を楽しみにしていました。Aさんに対し、周囲は丁寧に指導していましたし、Aさんも指示された際は、理解しているように見えました。ミスが増えてしまった際は、なぜ上手くいかないのか分からず、困惑してしまいました。
【Aさんと上司が取り組んだこと】
Aさんと上司で面談を実施しました。
【面談で分かったミスの背景】
ミスが少なかったOJTの頃は、Aさんは、指導係の社員から、業務を依頼されており、その際には優先順位も伝えられていました。しかし、OJTが終わってからは、一人で作業を進めるようになり、その頃から、多くの社員から同時に業務を依頼されるようになりました。結果、担当業務の把握が難しくなったり、依頼された業務をどれから手をつけていいのか分からなくなり、納期に遅れたり、忘れてしまったりしたようです。業務が上手く進められなくなった時に、指導係の社員に相談しようと思いましたが、忙しそうだったことや、「こんな内容を相談していいのか」と悩んでしまい、相談ができなかったとのことです。
実は、Aさんは障害特性上、マルチタスクや、業務の優先順位付けが苦手なこと、そして、相談の苦手さがあることは理解しており、このことは事前に上司や周囲の方に伝えていました。
しかし、上司や周囲の方の中で、次第に配慮事項の意識が薄くなってしまい、配慮が行き届かなくなっていました。また、Aさんも改めて言い出すことが出来ず、そのままになってしまっていたようです。
【実施した対応】
面談の結果、上記のようなミスの背景が分かってきたため、改めて業務指示者を決め、業務依頼の窓口を一元化すること、優先順位についてもサポートする体制を整えました。また月に1回、上司との面談を行い、状況共有や必要に応じて相談を行うこととしました。
【その後】
適切な配慮やサポートを得られたことで、本来のパフォーマンスを発揮できるようになり、ミスもほとんどなくなりました。また、持ち前の熱意を取り戻し、前向きに業務を進めています。
最後に
障害のある社員の方の業務の遂行に課題を感じられた際には、上記の内容を参考にしていただきながら、課題の「背景」に注目して頂き、状況を良くするにはどうしたらいいかを、障害のある社員と一緒に検討いただければと思います。
障害のある社員がつまづきやすいポイントとその対応や、定期面談のポイントについては以下にまとめておりますので、こちらもぜひ参考になさってください。
【関連記事】
【業務マネジメント】障害のある社員がつまずきやすい4つのポイントとその対応を紹介します
【面談方法】障害のある社員の定期面談の方法とそのポイントを解説します