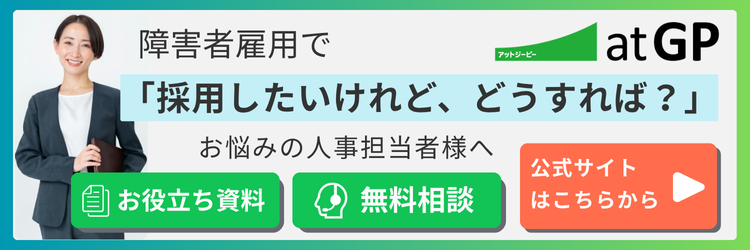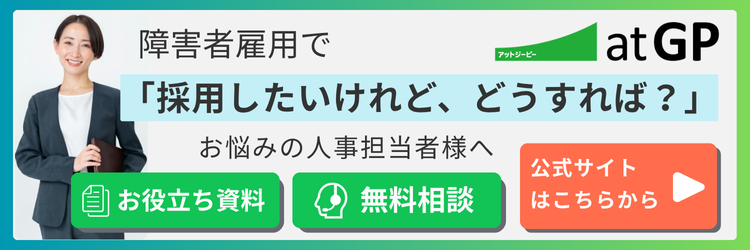障害者雇用では業務上の課題の「背景」に注目しましょう
入社後サポートをさせて頂いていると、本来はしっかりと業務を遂行できる能力やスキル、そして意欲がある障害のある就職者の方でも、障害特性やこれまでのトラウマによるつまずきが原因で、なかなか本来のパフォーマンスを発揮しきれていないというケースに出会うことがあります。
ただ、このような「つまずき」が背景であっても、企業側としては「この人は業務に必要な能力がないのではないか」と感じてしまい、こういった状況が続くと、中にはマネジメントをあきらめてしまうケースも多いように感じます。
しかし、このようなつまずきにより、本来の能力が発揮できていない場合、つまずきの原因を排除、もしくは低減することができると、本来のパフォーマンスを発揮できるケースも多いです。
また、このつまずきの背景や原因は小さな工夫や配慮で取り除くことができる場合が多いのも特徴です。
そのため、すぐに「能力がない」「仕事を任せられない」と諦めてしまうことはもったいないと感じますし、諦める前に、ぜひ障害のある社員とコミュニケーションを取り、「課題の背景は何か」「できない理由は何なのか」を一緒に掘り下げ、対策を検討頂きたいと思います。
今回はその手がかりとして、障害のある社員がつまずきやすいポイントとその対応をご紹介します。
つまずきやすい4つのポイントとその対応を紹介します
ポイント1 指示理解、業務理解、作業スピードでのつまずき
・特性と指示方法のアンマッチ
発達の特性上、口頭での指示や抽象的な指示が苦手な方がいらっしゃいます。こういった方の場合、苦手な方法で指示を受けると、内容の理解や把握が難しく、上手く業務が進められない場合があります。
【対処法】
障害のある社員と、どのような指示の仕方だと理解がしやすくなるかを確認しましょう。
本人の希望も踏まえ、文字や図を用いて伝える、本人がメモを取る時間を確保する、5W1Hを意識し具体的に伝えるといった工夫が有効です。
・疾患や薬の副作用による能力の制限
疾患や薬の副作用等により、運動機能の低下、記憶や判断といった認知機能の低下がみられ、作業効率や仕事の理解・判断力に制限が生じる場合があります。
【対処法】
まずは、焦らず業務が進められるスケジュールを設定しましょう。また、雑多な指示を避けること、業務の見通しが立つようなサポートも有効です。具体的には、業務指示者を決め、業務依頼を一元化したり、優先順位付けのサポートを行うといった工夫があります。また、以前は出来ていた業務が上手く遂行できないことで、自信を失ったり、自責心を持つ方もいますので、 出来ていることや努力に対するねぎらいの声かけを行うことも大切です。
ポイント2 コミュニケーション面でのつまずき
・周囲の評価への敏感さ
本人の性格や、過去のトラウマにより、周囲の評価に敏感で注意や指摘を過度に気にしてしまう場合もあります。その結果、萎縮してしまったり、緊張してしまい、本来の能力が発揮しにくくなってしまうことも多いです。
【対処法】
注意や指摘をする際は、感情的に接するのではなく、冷静に丁寧に伝えることを意識しましょう。
また、ポジティブなフィードバックも意識して行っていくことも大切です。
・相談の苦手さ
コミュニケーションの苦手さや、緊張、過去のトラウマなどから、自分から自発的にコミュニケーション相談することが難しい方も多いです。
【対処法】
まずは、こまめに声を掛け、会話や相談のきっかけを意識的に作っていくことが大切です。ただ、特に相談が苦手な方ですと、困っていても咄嗟に大丈夫と答えてしまう方もいらっしゃいます。困っていそうなのに、声をかけると「大丈夫です。」という返事が続く方の場合は、少し会話のラリーを重ねて頂き、「◯◯に困ってないですか?」「◯◯の相談先は分かっていますか?」等と、周りの方から一歩踏み込んだやり取りを行って頂ければ幸いです。
また、相談が苦手な方に対しては、定期面談を行い、定期的にじっくりと相談ができる仕組みを用意することも有効です。
そして、中には口頭でのコミュニケーションは苦手な方もいらっしゃいますので、その方の状況に応じて、日誌やチャットといった文字でのコミュニケーションも取り入れて頂ければと思います。
また、はじめは、周囲の方から声をかけて頂く必要があるかと思いますが、環境に慣れてきたり、相談に対する安心感を感じられると、障害のある社員から自発的に相談ができるようになっていくケースも多いです。
・言わなくてもわかるだろうという曖昧さ
企業と障者のある社員のどちらか一方でも「言わなくてもわかるだろうという」考えを持っていると、つまずきが発生しやすくなります。「言わなくてもわかるだろう」または、「言わなくても分かってほしい」という気持ちで過ごしてしまうと、様々な面で双方の認識のズレが大きくなりやすく、場合によっては何らかのトラブルに発展する場合があります。
【対処法】
伝えたいことは日々のコミュニケーションや面談を通して丁寧に明確に伝えていくことが大切です。
ポイント3 心理面でのつまずき
・偏見や無理解への不安
徐々に障害への理解も進んできていますが、やはり社会的な偏見や無理解を感じることがまだある状況です。過去にトラウマとなるような経験をもつ方もいらっしゃるため、健常者社員との壁を感じてしまったり、萎縮してしまっている場合もあります。このような状況だと、周囲との必要なコミュニケーションも抵抗が生まれ、相談や連携が難しくなり、本来のパフォーマンスを出せないことがあります。
【対処法】
職場に対する安心感を感じられたり、周囲の方との信頼関係を築いていくことが重要です。こまめに声をかける、仲間として受け入れていることを意識的に伝えることが大切です。
・体調不安と貢献意欲との葛藤
再発や体調悪化への不安を抱えている方も多いです。このような方は、体調維持のために無理はできないという気持ちと、もっと頑張りたい気持ち、頑張らないと存在価値がなくなってしまうのではないかという不安で板挟みになっている場合があります。このような葛藤がパフォーマンスを下げてしまうことも多いです。
【対処法】
まずは、再発や体調悪化の予防のため、通院や残業時間の配慮といった体調管理に必要な配慮を確認し可能な限り実施しましょう。また、こまめに体調について共有し、変化があれば都度対応を検討できる関係づくりを行っていきましょう。そして、本人が葛藤を抱えている場合は、本人の気持ちを傾聴しながら、不安や焦りを受け止めつつ、ポジティブなフィードバックを伝えたり、無理のない範囲でやりがいや貢献感を持てる業務を任せるといった工夫も有効です。
ポイント4 体調面でのつまずき
・疲れやすさ
生真面目で手を抜けない、常に緊張している、薬の服用から疲れやすいという方も多いです。
【対処法】
こまめに体調を共有したり、休憩の取り方相談しておき、予め休憩時間を設定したり、必要に応じて休憩を取れる体制づくりが有効です。
・変化への弱さ
人間関係の変化、立場の変化、生活の変化、仕事の変化等、変化に対しての弱さを持つ方も多いです。
【対処法】
こまめなコミュニケーションを取りながら変化を共有し、必要な対応を検討することが大切です。
【参照】
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 令和2年度版 就業支援ハンドブック(P223-P228,P238-P245)
最後に
障害のある社員の方の業務の遂行に課題を感じられた際には、上記の内容を参考にしていただきながら、障害のある社員と一緒に、課題の背景は何か、状況を良くするにはどうしたらいいかを検討して頂ければと思います。
ただ、つまずきやすいポイントやその対応は、個別性も高いため、障害のある社員とコミュニケーションを重ねて頂きながら、障害のある社員と貴社にあった対応を検討して頂ければと思います。
コミュニケーションの方法としては、面談が有効な手段の一つだと感じています。
業務の遂行に関する面談の方法については以下の記事にまとめてありますので、そちらも合わせてご覧ください。
また、対応に困った際は、主治医や産業医、支援機関担当者といった専門家のアドバイスも参考にして頂ければと思います。
【関連記事】
【面談方法】障害のある社員が想定よりも成果を出せない場合の対応を紹介します