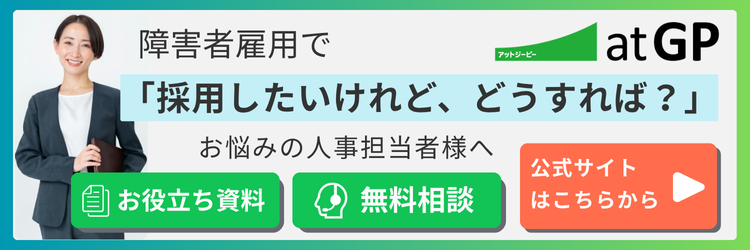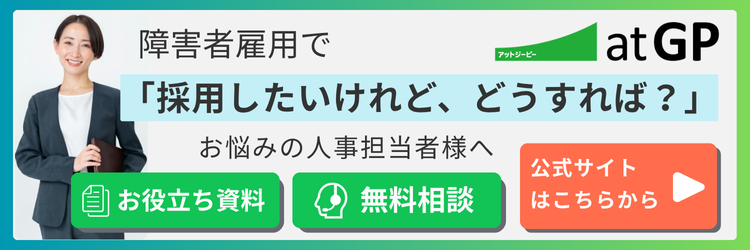要注意「手すきの時間が多い」と退職につながりやすい
意外だと感じる方も多いかと思いますが、弊社の入社後サポートの中で、退職を検討中や、退職された方のお話を伺うと「手すきの時間が多い」「業務が簡単すぎる」ことが退職理由に挙げられることも多いです。
この理由は、特にスキルを活かして働きたい、キャリアアップしたいといった志向性の方に多く「手すきの時間が多い」「業務が簡単すぎる」という状態が続くと、物足りなさや、存在価値の感じにくさ、今後のキャリアへの不安が強くなり、退職につながってしまうようです。
「手すきの時間が多い」背景には配慮と志向性のミスマッチが多い
障害者雇用において「手すきの時間が多い」「業務が簡単すぎる」という状況は、企業が障害に配慮し、あえて業務を減らしてくださっているからという場合が多いです。
本来このような配慮は非常にありがたいことです。しかし、折角頂いている配慮も、雇用している障害のある社員の志向性や希望とすれ違ってしまうと、企業側の意図に反して、退職の原因になってしまうことがあります。このすれ違いはなんとも、もったいないことだと感じます。
そして、これすれ違いは、双方がコミュニケーションを取り合うことで解消される可能性が高いとも感じています。そのため、このもったいないすれ違いや退職を減らすために、企業と障害のある社員で、志向性や希望する業務量、業務難易度について話し合って頂き、お互いが納得して働ける環境を整えていただければと思います。
以下に「手すきの時間が多い」ことによる退職を予防するためのポイントをまとめていますので、参考になれば幸いです。
「手すきの時間が多い」ことによる退職を予防するためのポイント
1 志向性を確認し、一人ひとりにあった業務を任せましょう
繰り返しになりますが、障害のある方も志向性は様々です。
障害特性や体調安定のため、定型業務を担当したい、ゆとりのある業務量で働きたいという方も多い一方で、スキルを活かして働きたい、キャリアアップをしたいという志向性の方もいらっしゃいます。
そのため、一人ひとり志向性をご認識頂いた上で、その方にあった業務をお任せ頂ければと思います。
志向性については、採用時にご確認頂くことと、入社後も定期的にご確認いただくことをおすすめします。
2 定期的にコミュニケーションをとりながら業務を調整しましょう
というのも、入社前に志向性や業務イメージを完璧にすり合わせることは難しいですし、志向性等は変化することも多いです。そのため、働く中で何らかの変化やギャップは生じるという前提のもと、双方の希望や認識のズレが大きくならないように、こまめにすり合わせを行っていただければと思います。
具体的には、面談等を行って頂きながら、以下の点を確認及び、すり合わせていただければと思います。
【コミュニケーションのポイント】
- 業務量についての確認しましょう
【質問例】
・業務量は多すぎて負担になっていませんか?もしくは少なすぎて物足りないことはありませんか?
- 業務の難易度について確認しましょう
【質問例】
・業務が難しすぎたり、簡単すぎたりしていませんか?
- 志向性について確認しましょう
【質問例】
・仕事にやりがいを感じていますか?やりがいを感じるのはどんな時ですか?
・〇カ月後、〇年後はどんな仕事をしていたいですか?
・今後、挑戦してみたい業務はありますか?
- 1~3の内容も踏まえつつ、今後の業務について相談しましょう
障害のある社員の中には、今後の見通しが分かると安心感を感じる方も多いです。
そのため、直近の業務内容に加え、この先3か月、6カ月の業務イメージも共有しましょう。
- その他
体調や人間関係等、業務内容以外のことも含め、困っていることや不安に感じていることがないかも確認しましょう。
3 メイン業務とサブ業務を組み合わせた業務設計も検討してみましょう
「手すきの時間が多い」背景には、業務負荷を上げることで、体調が悪化してしまうのではないかという不安や、体調によっては急なお休みが発生する可能性もあること等から、障害のある社員の希望があっても、なかなかまとまった量や一定の責任や納期があるような業務はお任せしにくいという場合もあると思います。
もし、このような不安がある際は、以下のような2種類の業務を組み合わせて業務をお任せすることがおすすめです。
メイン業務…職場としても可能な限り確実に遂行してほしい業務
・職場に対し貢献度が高い業務
・納期がある業務
👉体調管理の負担になりすぎない程度でお任せしましょう。
サブ業務…時間があるときにコツコツ進めてもらいたい業務
・緊急性が低い業務
👉書類の整理やPDF化、マニュアル作成等。
それぞれの難易度や量については、こまめに相談しながら調整していきましょう。
【コラム】コロナによる業務不足に不安を感じる社員も増加中
新型コロナウイルスの流行により、事業環境や働き方が変化し、障害者雇用でお任せ頂くことが多い、事務系、庶務系の業務が減少または無くなってしまった企業も多いかと思います。
まず、これは企業としても不測の事態であり、悩ましい状況かと思います。
一方でやはり、この業務不足の状況に対し、不安を感じる障害のある社員も増えています。
不安の内容としては、通常の「手すきの時間が多い」「業務が簡単過ぎる」場合の不安に加えて、非正規雇用で働く方が多いことから、雇用の継続への不安を感じる方も増えているという状況です。
また、その不安から少数ではありますが、転職を検討する方もいらっしゃる状況です。
そのため、もし新型コロナウイルスの流行により、障害のある社員に依頼している業務が減少しているなどの変化が生じている状況でしたら、可能な範囲で構いませんので、以下の点などについて障害のある社員とコミュニケーションをとって頂ければと思います。
コミュニケーションのポイント
・新型コロナウイルスの流行による事業環境や業務の変化についてのご説明
・今後の業務依頼についての見通し
・評価や雇用継続についての見通し
👉特に、少ない業務であっても通常通り評価していること、今後も雇用を継続する見通しであること等、安心感につながる情報はこまめに共有頂けますと幸いです。
最後に
様々ある退職理由の中でも「手すきの時間が多い」「業務が簡単すぎる」といった退職理由は、企業と障害のある社員でコミュニケーションを取り合うことで、比較的、予防や改善が見込める可能性も大きいのではないかと感じています。今回の記事が、このような退職を 少しでも減らす参考になれば幸いです。コミュニケーションの方法としては、日々のコミュニケーションに加え、定期面談といった相談できる仕組みの導入を進めしています。定期面談の方法につきましては以下をご覧ください。
【関連記事】
【面談方法】障害のある社員の定期面談の方法とそのポイントを解説します